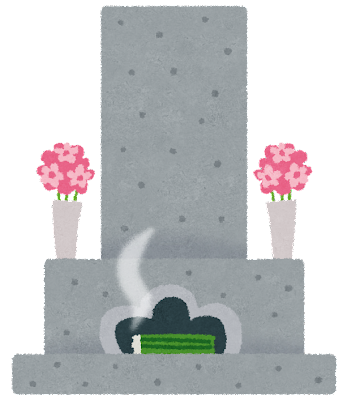形で分かる墓石の意味
和型墓石
位牌を模した形からできあがってきたものです。
構成は、竿石(仏石、石碑など)、上台、下台の二重台型が全国的に一般的です。
竿石には様々な加工様式があります。
東海地方では下台の事を四ツ石と言い上台と四ツ石の間に中台と言うお骨を入れる入口のついた石があります。
それ以外にも竿石の下にはスリンや蓮華台と言った座布団や芝台といった四ツ石の下にもう一段つけることが多いです。
五輪塔(ごりんとう)
密教において、空・風・火・水・地は物質を構成する5つの要素であり、「五大」と言います。
上より、空・風・火・水・地の順で構成されています。
これに対応する部分に五大・音や梵字を彫り込み形も組み合わせて出来ています。
五輪塔だけでもお墓にはなるのですが、その他の祀り方として、50回忌33回忌で神上がりをすると言われてそれ以降の法要はおこないません。神上がりをしたご先祖様を祀るためのお墓としても使われます。
無縫塔(むほうとう)
竿石が丸い卵型のお墓の事です。
おもに僧侶のお墓として建てられます。
神道型
「天の叢雲の剣(あめのむらくものつるぎ)」を模したと言われる四面錐体型の場合が多く竿石の頭が尖ったお墓になります。
木・塔婆立てのお墓
お墓を建てずに納骨した場合に建てる事があります。
基本は1年後にきちんとしたお墓を建てるまでの仮のお墓となります。